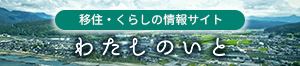本文
結核をご存じですか?
結核とは
結核菌が体の中に入り、増えることによって主に肺に炎症を起こす病気です。腎臓やリンパ節、骨、脳など肺以外の部位に影響を及ぼすこともあります。
結核菌は人から人へとうつる感染症であり、二類感染症に指定されています。
加齢や病気により免疫力が低下しやすい高齢者の発症が多い傾向にありますが、若い方でもかかる病気です。
結核は昔の病気ではありません
結核は全国で毎年1万人以上の患者が新たに発生している、国内最大の感染症です。医療の発達や生活水準の向上により結核による死者数は減少傾向にありますが、今でも年間約1,600人が結核で亡くなっています。
「空気感染」で感染します
結核を発症している人が咳やくしゃみをすると、結核菌を含んだ飛沫(しぶき)が空気中に飛び散ります。それを他の人が吸い込むことで感染します。
「感染」と「発病」は異なります
感染とは
結核菌を吸い込み、肺の奥に結核菌が住み着いた状態を「感染」といいます。
結核菌を吸い込んでも、多くの場合は体の抵抗力により追い出され、鼻やのどで菌が消えれば感染しません。
感染しただけでは、体に悪い影響はなく、周囲の方に感染させることもありません。
発病とは
結核菌が体の中で活動を始め、菌が増殖して様々な症状が現れることを「発病」といいます。症状が出始めると周囲の方に感染させることがあります。
感染者のうち、感染から半年~2年程度の間に発病する方は約10%、感染後数年~数十年後免疫力が落ちた時に発病する方は約20%、残り約70%は一生発病しないと言われています。
感染はしているが発病していない方(潜在性結核感染症)は、予防薬を服用することで発病のリスクを低下させることができます。
結核を発病すると・・・
症状
咳や痰、発熱など風邪に似た症状が2週間以上続くのが特徴です。血痰や食欲低下、体重減少などの症状が見られることもあります。
上記のような症状がなく発症する場合も多く、結核は発見が遅れがちです。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
治療
結核治療の基本は、規則正しく薬を飲むことです。標準的には、3~4種類の薬を最低6か月以上内服します。
きちんと治療していれば、周囲の方に感染させる心配はありません。
結核を予防するためにできること
1.咳や痰などの症状が2週間以上続いたら、早めに医療機関を受診しましょう
2.規則正しい生活を心がけましょう
バランスの良い食事と十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めておくことが大切です。
3.1年に1回は胸部レントゲン検査を受診しましょう
定期的に胸部レントゲン検査(胸部健診)を受診することにより、結核の早期発見・早期治療につながります。
なお、65歳以上の方は、年に1回胸部健診(結核健診)を受けることが義務づけられています。
糸魚川市では、市民の方を対象とした健診を実施しています。職場などで健診を受診する機会がない方は、ぜひご活用ください。
詳細は令和7年度健康診査・各種がん検診をご覧ください。
4.1歳未満はBCGを接種しましょう
生後1歳までにBCGワクチンを接種することにより、小児の結核の発病を50~70%程度、重篤な髄膜炎や全身性の結核に関しては60~80%程度予防することができると報告されています。
糸魚川市では、1歳未満のお子さんを対象にBCGの定期予防接種を実施しています。
詳細はこどもの予防接種(個別接種)をご覧ください。