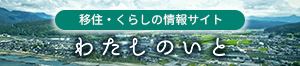本文
国民健康保険から受けられる給付
給付とは
病気やけがをしたときは、病院や薬局で保険証を提示すれば、医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、次のような診療を受けることができます。
- 診察、治療、調剤
- 入院、看護
- 訪問看護 など
医療機関で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりです(残りの費用は国民健康保険が負担します)。
年齢別 医療費の自己負担割合
|
小学校就学前の方 |
2割 |
|---|---|
|
小学校就学後から69歳の方 |
3割 |
|
70歳から74歳の方 |
2割 |
※現役並み所得者とは
同じ世帯で国保に加入している70~74歳の方に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
ただし、次の方は2割負担となります。
(1)対象者の収入の合計が383万円未満(対象者が2人以上のときは520万円未満)であり、市役所健康増進課、能生・青海事務所に申請した方
(2)平成27年1月以降70歳になる国保被保険者(昭和20年1月以降生まれ)が同一世帯にいる場合、世帯の70歳以上の国保被保険者の所得(総所得金額から基礎控除33万円を引いた額)合計額が210万円以下の方
高額療養費
次のようなときは、申請すると高額療養費として世帯主に支給されます。
- 同じ月内の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えたとき
- 同一世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担が2件以上あった場合、その合計が自己負担限度額を超えたとき など
自己負担限度額や高額療養費の支給申請について、くわしくは医療費が高くなったときのページをご覧ください。
いったん全額自己負担したとき(療養費)
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると上記自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※柔道整復師の施術等では、「受領委任」という方法が認められており、病院・診療所に受診するときと同様に、自己負担額を支払うことで施術を受けることができることがあります。
|
医療の内容 |
申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病や旅行先など、やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき |
|
| 医師の指示でコルセットなど(治療用装具)を作ったとき |
|
| 海外渡航中に急病等で医療機関にかかったとき(海外療養費) |
|
| 医師から指示された、はり・きゅう・マッサージ代 (注1) |
|
| 国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折・脱臼・ねんざなど) (注2) |
|
| 輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) |
|
(注1)
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
主として神経痛、リウマチ、頚(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症状とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などおたずねください。
保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象となりませんので、ご注意ください。
マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、マッサージ施術所などにおたずねください。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
(注2)
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
単に肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等で治療中の方は、施術を受けても保険等の対象となりませんので、ご注意ください。
申請書ダウンロード
国民健康保険 療養費支給申請書 [PDFファイル/429KB]
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。
くわしくは国民健康保険出産育児一時金の支給方法についてのページをご覧ください。
葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなられると、葬祭を行った方に、葬祭費として50,000円支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証
- 申請者(喪主)名義の通帳
- 印鑑
※1 申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です
※2 死亡時に国民健康保険に加入していても、次の場合は以前に加入していた健康保険から葬祭費(または埋葬料)が支給されます。詳しい手続き方法は以前加入していた健康保険にお問い合わせください。
(1)死亡前3か月以内に、以前加入していた健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた場合
(2)死亡時または死亡前3か月以内に、以前加入していた健康保険から傷病手当金の継続給付を受けていた場合
(3)死亡時または死亡前3か月以内に、以前加入していた健康保険から出産手当金の継続給付を受けていた場合
申請書ダウンロード
国民健康保険 葬祭費支給申請書 [PDFファイル/217KB]
入院時の食事代
入院したときの食事代は、他の診療にかかる費用などとは別に食費の一部を負担していただきます(残りは国民健康保険が負担します)。
なお、食事代は高額療養費の支給対象外です。
| 1 | 一般(2・3以外の方) | 1食490円 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は住民税非課税世帯低所得2の方) |
過去1年間の入院が90日以内 | 1食230円 |
| 過去1年間の入院が90日を超える | 1食180円 | ||
| 3 | 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない方 (70歳以上の方で、住民税非課税世帯低所得1の方) |
1食110円 | |
所得区分、認定証の交付については医療費が高くなったときのページをご覧ください。
※住民税非課税世帯の方へ
住民税非課税世帯の方は、申請することにより上記2、3の金額になります。
市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をし、入院の際に医療機関に提示してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 過去1年間で入院された分の領収書(住民税非課税世帯の方のみ)
- マイナンバー