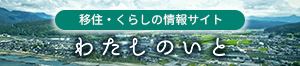本文
固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
| 土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
税額
課税標準額×税率(1.4%)が税額となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額が算定されます。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
評価替えについて
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第二年度(翌年度)及び第三年度(翌々年度)は、地目変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
※次回評価替えは令和9年度です。
土地の価格については、上記のように原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、据置年度においても地価の下落傾向が見られる地域については、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を同年1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 課税標準額×税率(1.4%)が税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合、また土地について税負担の調整措置が適用される場合においては、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点
同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目別の評価方法
| 地目 | 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
|---|---|
| 地積 | 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。 |
| 価格 | 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |
市街地における宅地の評価方法(路線価方式)
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分する。
▼
標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
▼
主要な街路の路線価の付設
▼
その他の街路の路線価の比準、付設
▼
地区・地域内の各筆の評価
(注意)平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
『路線価』についてはこちらをご覧ください。
(『全国地価マップ』財団法人資産評価システム研究センター<外部リンク>)
その他の宅地、農地、山林の評価方法(標準地比準方式)
標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。(農地や山林において、その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込み地としての要素等があればそれに相当する価格を控除した純農地、純山林としての価格に比準して評価します。)
牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般の住宅用地に分けて特例措置が適用されます(住宅の延床面積の10倍を限度)。
|
区分 |
面積 |
課税標準の特例 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分) |
価格の6分の1 |
| 一般の住宅用地 | 上記以外の住宅用地 |
価格の3分の1 |
家屋に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
| 再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費 |
|---|---|
| 経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価額は引き上げることなく、原則として前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合(※)
(※)建築物価の変動割合は、固定資産評価基準により定められます。
償却資産に対する課税のしくみ
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
その内容を例示すると、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)などの事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用としている場合は、償却資産として課税の対象となります。
なお、下記の場合は課税対象となりません。
A 耐用年数が1年未満の資産
B 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産) C 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
D 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(B・Cの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)= 取得価額 ×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)より小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
|
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
| 減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 [定率法選択の場合]
|
一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
| 前年中の新規 取得資産 |
月割償却 | 半年償却(2分の1) |
| 圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
| 特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度有り | 制度無し |
| 増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度有り | 制度有り |
| 評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
| 改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
関連情報
都市計画税の概要
固定資産税(家屋)の軽減措置
償却資産の申告
市税に関する証明書の申請方法
市税に関して不服のあるときは(課税等に対して)