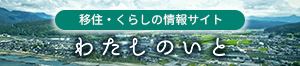本文
その他の文化財
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
風俗慣習「バタバタ茶」
“バタバタ・・・”と竹製の茶筅(ちゃせん)で音を立てながら泡立った番茶(黒豆や青葉、茶花など)をいただく「バタバタ茶」は珍しい振茶(ふりちゃ)の習俗の一つです。全国的にみても現在残っているのは沖縄県(ブクブク茶)、島根県(ボテボテ茶)、富山県(バタバタ茶)。新潟県内でも糸魚川市のみに残っています。多少の作法や茶会の決まりごとはあったようですが、茶道のような堅苦しいものではなく、どちらかといえばコミュニケーションや慰労の意味で行われています。

古文書「伴家文書」
戦国時代の武将上杉謙信の家臣である山本寺(さんぽんじ)氏に仕えたとされる伴家は江戸時代になると大肝煎(おおきもいり=代官と村役人の中間的な職)として活躍しました。その伴家に残る戦国時代から明治以降の古文書や絵地図の数は約1,600点。その中には上杉時代の台帳や江戸元禄期以前の検地帳や年貢関係資料、さらには村の土地・財産・年貢関係資料など比較的良好な状態で残っています。