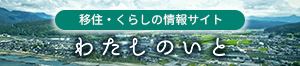本文
農地転用(農地法第4条・第5条等)
1.農地法第4条及び第5条(農地転用)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、耕作の目的に供されている土地を宅地や資材置場、駐車場などの農地以外の用途に変更することをいい、この行為を行うには農業委員会長または県知事の許可が必要です。
農地転用には、自己所有地を転用する農地法第4条と自己所有地以外を転用する農地法第5条による転用があります。
なお、対象農地が農業振興地域内の農用地である場合は、その除外(農振除外)を行ったうえで、転用の手続きになります。
あらかじめ農林水産課農村振興係までお問合せください。
|
農地の所有者 |
該当 |
申請 |
|---|---|---|
|
自己所有の農地を転用 |
農地法第4条 |
転用者の単独申請 |
|
他人所有の農地を転用 |
農地法第5条 |
譲渡人、譲受人の双方による共同申請 |
許可権限者
農地転用許可は、農地転用の面積に応じて農林水産大臣、新潟県知事または糸魚川市農業委員会長が許可します。
- 糸魚川市農業委員会長の許可
転用面積が同一事業目的に4ヘクタール以下の場合 - 農林水産大臣(北陸農政局長)の許可
転用面積が同一事業目的に4ヘクタールを超える場合
農地転用の許可基準
申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可することができます。
(1) 立地の基準
農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準です。
|
農地区分 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
原則不許可 |
農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地 |
|
第1種農地 |
10ヘクタール以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地 | |
|
許可 |
第2種農地 |
市街地化が見込まれる農地または山間地等の生産性の低い小集団の農地 (上記原則として許可しない農地、及び第3種いずれにも該当しない農地) ただし、既存宅地・周辺の第3種農地等に立地することができない場合に限る。 |
|
許可 |
第3種農地 |
市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
(2) 一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。
- 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
- 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 農地転用を行うに当たり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、または処分の見込みがない場合
- 周辺の営農条件に悪影響を与える恐れがある場合
- 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合
よく受ける相談
|
相談内容 |
手続き・対応 |
|---|---|
| 田や畑を耕作目的以外に使いたい | 農地を耕作目的以外で使用する場合、自分の農地であっても農業委員会長または県知事の転用許可が必要です。(ただし、耕作をする上で必要となる農業施設の場合は届出(かい廃届)による農業委員会の承認ですむこともあります) |
| 申請をしたが、早く工事を始めたい | 工事を始めるには農業委員会長または県知事許可となります。その間に工事を始めることは許されません。許可前に整地や着工等の工事を始めると工事の中止やせっかく作ったものを壊して元に戻すよう農業委員会長から命令が出ることがあります(原状回復命令)。 |
| 許可を受けたが、気が変わり当初の内容と違うもの目的で使いたい | 当初の許可と違う目的に使用する場合や転用者が変わる場合、変更手続き(事業計画変更)が必要であり、農業委員会長または県知事の許可が必要です。変更手続きなしに当初の目的以外の転用をすると農業委員会長または県知事より原状回復命令が出ることがあります。 |
2.農地法第4条・第5条・かい廃届の申請締切日
申請の締切日は、毎月5日です。(5日が土曜日、日曜日、休日の場合は、その前日が締切日となります。)
※締切日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意ください。
また、添付書類に不足や不備等がありますと当月分として受付できなくなるので、ご注意してください(書類提出を受けてから許可までは、約2か月かかります)。
なお、各申請の用紙は農業委員会事務局に用意してあります(様式集でダウンロードできます)。
3.違反転用
違反転用とは、農地法の許可を受けないで農地を転用した場合や許可条件に違反して転用されている場合などをいいます。これらの違反をしますと、転用者に対して農業委員会長または県知事がもとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は、最高3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もありますので、十分に注意してください。