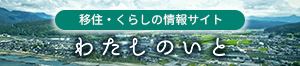本文
個人市民税の計算方法
税額の計算(均等割・所得割)
市民税は「均等割」と「所得割」の合計です。
1 均等割
| 区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
|---|---|---|---|
| 県民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
| 市民税 |
3,500円 |
3,000円 | |
| 国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 | |
※平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災を教訓とした防災対策のため、個人市民税県民税の均等割をそれぞれ年額500円引き上げていました。この臨時的措置が終了しましたが、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
※一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人も課税されます。
2 所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)
課税総所得金額×税率-税額控除額=所得割額
※個人県民税についても同様の計算を行い、個人市民税とあわせて徴収されます。
※市民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除額が異なります。たとえば基礎控除額が所得税は48万円の場合、市民税は43万円になります。配偶者控除、扶養控除の額は所得税がそれぞれ38万円なのに対し、市民税は33万円です。
これは、住民税としての性格から、所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっていることによります。
所得割の税率
|
市民税 |
県民税 |
|
|---|---|---|
|
税率 |
6% |
4% |
所得の種類と金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、所得税と同様10種類で、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。
|
所得の種類 |
内容 |
所得金額の計算方法 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所得 | 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬が生じる所得 | 収入金額-必要経費 | ||||
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | ||||
| 利子所得 | 預貯金、公債、社債などの利子 | 収入金額 | ||||
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 | ||||
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 | ||||
| 譲渡所得 | 土地、家屋、機械などの資産を売却した場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額 | ||||
| 一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 | ||||
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | 収入金額-退職所得控除額×1/2 | ||||
| 山林所得 | 山林を売却した場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | ||||
| 雑所得 | 公的年金、個人年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
|
||||