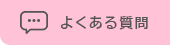本文
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある方は20歳未満)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
- 手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(受給資格者が父であるときを除く)
児童扶養手当法の一部改正
平成26年12月改正
以前は、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに手当を受け取れる場合
- 父母のいないお子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
令和3年1月改正
令和3年3月分(5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されます。
手当の支給額(月額)
請求者(受給者)や同居(同住所地で住民票を世帯分離している世帯を含みます)している扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年分(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が下表の所得制限限度額と比較して一定の額を超えている場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
支給月額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動スライド制」がとられています。
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
|
2人目以降 |
10,750円を加算 | 11,020円~5,520円を加算 |
所得による手当の支給制限
請求者(受給者)の前年分(1月から10月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除額、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の所得制限限度を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
|
年 |
令和7年 |
令和8年 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
月 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
1 |
3 |
5 |
|
判定所得 |
令和6年 |
令和7年 |
|||||||
所得額
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-諸控除額-80,000円(社会保険料相当額)
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その所得より最大10万円が控除されます。(双方に係る所得がある場合は、双方を合計した所得額より最大10万円)
※養育費とは、受給資格者が母または父の場合に、児童の父または母から児童の養育に必要な費用の支払として受ける金銭や有価証券を指します。。
諸控除額
|
控除内容 |
控除額 |
|---|---|
| 雑損控除、配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
| 障害者控除 |
27万円 |
| 特別障害者控除 |
40万円 |
|
寡婦控除(請求者が父母の場合は除く) |
27万円 |
|
ひとり親控除(請求者が父母の場合は除く) |
35万円 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
所得制限限度額
|
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者・配偶者等 |
|
|---|---|---|---|
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
69万円 (142万円) |
208万円 (334.3万円) |
236万円 (372.5万円) |
|
1人 |
107万円 (190万円) |
246万円 (385万円) |
274万円 (420万円) |
|
2人 |
145万円 (244.3万円) |
284万円 (432.5万円) |
312万円 (467.5万円) |
|
3人 |
183万円 (298.6万円) |
322万円 (480万円) |
350万円 (515万円) |
|
4人 |
221万円 (352.9万円) |
360万円 (527.5万円) |
388万円 (562.5万円) |
|
5人 |
259万円 (401.3万円) |
398万円 (575万円) |
426万円 (610万円) |
|
以降1人増すごとに38万円加算した額 |
|||
※扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額を所得制限限度額とします。
(1)請求者(受給者)の場合
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者等の場合
・老人扶養親族1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
手当支給日
| 支給対象月 | 手当支給日 |
|---|---|
| 3月~4月分 | 5月11日 |
| 5月~6月分 | 7月11日 |
| 7月~8月分 | 9月11日 |
| 9月~10月分 | 11月11日 |
| 11月~12月分 | 1月11日 |
| 1月~2月分 | 3月11日 |
※なお、支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の平日が支給日となります。
認定請求の手続
手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。手当を受けようとする方は、なるべく早く認定請求の手続きをしてください。手当は認定請求をした日の翌月分から支給されます。
【認定請求に必要な書類等】
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例:個人番号カード、個人番号通知書または通知カード(氏名、住所等に変更がない場合)など - 本人確認書類
例:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど - 年金手帳または年金証書
- 通帳など口座情報が分かるもの
※申請内容により、必要書類が異なります。詳しくは担当窓口でお問い合わせください。
手続き一覧表
次のような場合には、必ず届け出てください。
|
手続きが必要なとき |
|---|
|
氏名、支払金融機関(名義等)を変えたとき |
|
他市町村へ転出するとき、または市内で転居するとき |
|
児童数が増減したとき(施設入所・里親委託を含む) |
|
所得の高い扶養義務者と同居若しくは別居するようになったとき、 または所得の修正申告等をしたとき |
|
児童を監護しなくなったとき(施設入所・里親委託を含む) |
|
受給者が公的年金等を受給できるようになったとき |
|
受給資格がなくなったとき |
(注1)毎年8月に、更新の手続きが必要です。対象者へ7月下旬に書類一式を送付します。必要書類を持参の上、期限内に手続きをしてください。なお、オンライン(ぴったりサービス)で申請可能です。詳しくは「行政手続のオンライン申請開始」
現況届を2年間提出しない場合は、請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
(注2)法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合、また、同居していなくても定期的な訪問があり、生計を同じくしている場合にも事実婚が成立しているとして手当が受けられなくなります。
(注3)届出をしないで手当を受けていると、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになりますのでご注意ください。